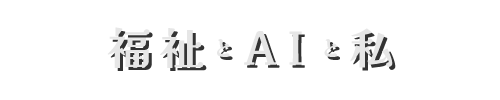福祉なんて自分には関係ない?
自分もそうだった。この世界に関わるまでまったく興味もなかったし、知るつもりもなかった。
でも、ある日突然その中に放り込まれて、少しずつ「制度の違和感」や「他人の人生に関わる重さ」に引っかかるようになった。
このブログは、そんな“福祉に興味ない人”に向けて書いています。
たとえば「Vtuber」とか「界隈」とか「推し」みたいに、ある世界に深く関わってる人たちが持ってる独特の距離感や関係性のあり方ってあると思う。
福祉も、そういう“見えづらいけど大事な関係性”をつくってる世界なんじゃないかと感じてる。
だからこそ、福祉の話をただ制度としてじゃなく、思考の切り口として、自分ごとに近づける形で綴っていきたいと思っています。
福祉に興味ゼロだった過去
福祉なんて、正直まったく興味なかった。
この仕事につく以前は、観光ガイドや情報発信、デザインの仕事をしてた。
でも、コロナで観光客が激減。どれだけ努力しても、生活そのものが立ち行かなくなった。
そのとき、知り合いの福祉施設に「とりあえず」でバイトに入った。それだけ。
ほんとに、ただの偶然。
制度のことも、現場のことも、まるで知らなかったし、知りたいとも思ってなかった。
気づいたら現場にハマってた
なのに、気がついたら正職員になってた。
資格も取って、気がつけば福祉制度の根本について考えてるような自分がいる。
自分でも「何やってんの?」ってなるけど、気持ちは静かに燃えている感じ。
やればやるほど、奥が深すぎてわけがわからなくなる。それでも目の前の人に向き合うしかない。
嫌なこともたくさんあるけど、そんな現場に、気づけば惹かれていた。
「介護って面白いよ」の意味
仕事を始めたばかりの頃、上司がふと言った「介護って面白いよ」って言葉。
当時は意味がわからなかった。でも、頭の片隅にずっと残っていた。
知識が増えるたび、人との関わりが深まるたびに、少しずつその意味が体感としてわかってきた。
面白いっていうか、むしろ人の生き様っていうか、どうしようもない弱さに、真正面からぶつかるしかない場所だった。
もともと知識を得るのが好きだったし、そう言う意味で自分に合っていたのかもしれない。
学び始めたら足りなさに気づいた
介護福祉士の勉強を始めて、他の施設の職員たちと自分を比べてみて、知識も経験も圧倒的に足りてないことに気づいた。
悔しかったから、とにかく詰め込んで勉強した。
試験では高得点を取れた。それが誇らしくて、上司に報告した。
でも返ってきたのは、「俺より点がいいからって当てつけか?」という皮肉。
褒めてもらえると思ってたから、正直キツかった。
でも、それが現場のリアルなんだと割り切った。
社会福祉士を目指して見えてきた世界
介護福祉士を取ったら目標を失った。
ケアマネを取るには時間がかかる。介護福祉士取得から5年のキャリアが必要とか長過ぎて萎える。
だから、その間に何かをしたかった。
代表に相談して、「社会福祉士っていう選択肢もある」と聞いた。
調べてみて、すぐに「これだ」と思った。
通信大学に入り、スクーリングや実習を通して、福祉の世界の奥行きに衝撃を受けた。
障害、児童・家庭、貧困、権利擁護、地域包括ケアシステム、社会学、心理学、刑事司法……
自分がやっていた「介護」は、そのごく一部だった。
「福祉を語れない自分」への違和感
「福祉って何?」この質問に答えられる人ってどれくらいいるのだろう。
福祉の現場で働いているのに、福祉について語れない。
そんな自分に違和感を覚えるようになった。
それを語るってことは、当然知識が必要だし、考え続けることでもある。
相手のことを知るために、まずは自分と向き合わなければならない。
福祉に触れれば触れるほど、「ちゃんと語れる自分になりたい」と思うようになった。
障害福祉の現場で感じた制度の限界
大学の実習では、重度の障害を持つ人たちと関わった。
目の前の生活がいかに制度によって支えられ、逆に制限されているかを目の当たりにした。
きれいごとでは済まない現実。
制度があるからこそ、生きていける人がいる。 でもその一方で、制度からこぼれ落ちる人たちもいる。
その不均衡の中で、自分がどれほど無力なのかを痛感する日々だった。
福祉制度は、複雑すぎて動かせない?
福祉制度は、ひとつの仕組みじゃない。
障害、子ども、高齢者……それぞれに異なる歴史や文化的背景があって、縦割りのまま重なり合っている。
制度をひとつ変えようとすると、繊細なバランスが崩れる。
なぜなら、抑圧されてきた人々の声や感情が、その中に積み重なっているから。
今まで可視化されなかったものが表に出ると、それを無視できずに制度に上乗せされ、さらに複雑に絡まっていく。
もう修正も統合も簡単にはできない。だけど、ゼロから作り直すのも現実的ではない。
頼れる上位概念といえば、せいぜい憲法くらいだ。
そんな中で、現場は制度にどうつなげるかを模索し続けている。
でも、法制度には線引きがあって、どうしてもこぼれ落ちる人が出てくる。
その部分を、少しずつでも解きほぐしていきたいと思っている。
ChatGPTで問い直す日々
大学で学ぶ中で、ChatGPTに出会った。
最初はただただすごいと思った。なんでも前向きに答えてくれる。万能感さえ感じた。
でも、知識が浅いと、質問しても深い答えは返ってこない。
逆に言えば、「どんな問いを立てるか」が重要だと気づいた。
自分の無知に直面しながらも、そこから問いを立て直すことで、見えるものがあった。
制度の前提をひっくり返す視点。それを与えてくれた。
福祉は「考え方」になった
福祉について考えるようになって、社会の見え方がまるで変わった。
自分の視点が変わることで、身近な人との接し方も、ニュースの捉え方も変わっていった。
「これって、自分にもできることあるかも」と思えるようになったとき、 福祉的な思考を持つことで、もしかしたら社会全体も少しずつ変わっていけるんじゃないか。 そんな希望のようなものを感じるようになった。
福祉って、支援の方法だけじゃなくて、社会のあり方そのものを問うものだと思うようになった。
誰が、どんな選択肢を持てるか。 どんな関係性を築けるか。
そして、それを誰と、どんな環境で実現していけるのか。
福祉は、「あたりまえ」を問い直す視点であると同時に、 それを支える力や仕組みを整えるための試みでもある。
できれば、福祉がなくても生きやすい社会にしていきたい。
でも、まだまだその途上にある今は、必要な支えとして存在している。
それを知ることで、世界の見え方が変わるかもしれない。 その変化を、誰かと共有したい。
ただ、それだけ。
書く理由
今、福祉は岐路に立っている。
少子化が進み、リソースは先細り。現場の声が届かないまま、制度だけが更新されていく。
それでも、現場にいる自分たちが声をあげなかったら、何も変わらない。
だから、書く。
現場で感じた違和感、小さな引っかかりを、言葉にする。
かたくるしい論文じゃなくて、皮肉もちょっと混ぜて、思わずクスッと笑えるような表現で。
でも、その奥に残る違和感とか、「これって本当にこのままでいいの?」っていう問いかけをそっと忍ばせたい。
福祉の現場で感じた矛盾や不条理を、ただ叫ぶでもなく、無理に希望に変えるでもなく、そのままの温度で届けたい。
そんな言葉を探し続けることが、今の自分にできる精一杯のソーシャルアクションだと思うから